免許更新の流れとは?運転免許証の時期や費用の目安を紹介

運転免許証は、最初に交付されたものが一生使えるわけではありません。有効期限があるため、指定された期間の間に免許更新の手続きが必要です。
しかし、初めて免許更新を迎える方や免許証の区分が変わった方は「どのような手続きが必要なのか」「時期や費用はどのくらいなのか」など、分からないことも多いのではないでしょうか。
この記事では、運転免許証更新の一連の流れと時期、費用の目安を解説します。免許更新の流れを知ることで、事前に日程や時間の調整や必要な持ち物の準備ができるでしょう。
※目次※
・運転免許の更新は流れがシステム化されているため、必要なものさえ持参すればスムーズに更新できる。
・免許証の区分によって必要な持ち物や講習の時間、費用が異なるため、更新案内はがきを確認しておこう。
・有効期間内に免許更新ができなかった場合は、速やかに申請すると簡単に再取得できる。
免許更新の流れを確認しよう

運転免許証の更新期間が近づくと、更新はがきが届きます。初めて免許更新を迎える方は「どこでやるのか」「何が必要なのか」「どのような手続きが必要なのか」など、分からないこともあるでしょう。
ここでは、免許証更新の時期や大まかな流れ、免許証の有効期限を解説します。
更新は誕生日の前後1か月で行う
運転免許証の更新は、道路交通法第101条第1項により「有効期間が満了する日の直前に迎える誕生日の1か月前から、有効期間満了までの間に行う」と定められています。
有効期間の満了日は誕生日1か月後のため、誕生日の1か月前~1か月後までに手続きが必要です。
更新期間が近づくと公安委員会から更新連絡はがきが送付されます。郵便事故で届かないリスクもあるため、失効を防ぐためにも更新時期は覚えておきましょう。
検査や講習を受けて免許証を受け取る
運転免許の更新は、各都道府県の公安委員会が指定する場所での手続きが必要です。免許更新の流れを把握しておきましょう。
1.免許を更新できる施設へ行く
2.更新申請をする
3.適性試験を受ける
4.更新時講習を受講する
5.免許証の交付を受ける
免許更新時には、適性試験や更新時講習の受講が必要です。更新時講習を実施している時間は施設によって異なるため、状況によっては待ち時間が発生し、手続きが完了するまでに時間がかかるでしょう。
有効期間の長さは運転免許証の色で変わる
運転免許証は、運転免許を継続している期間の交通違反やけがのある事故の有無により、5つの区分に分けられています。有効期限の長さはこれらの区分によって異なるため、区分別に分けられた免許証の色と有効期限をチェックしましょう。
|
区分 |
詳細 |
免許証の色 |
有効期限 |
|
新規取得者 |
初めて免許を受ける人 |
緑 |
3年 |
|
初回更新者 |
継続している期間が5年未満、違反運転者講習の区分に該当しない人 |
青 |
|
|
一般運転者 |
継続している期間が5年以上、3点以下の違反が1回の人 |
5年 |
|
|
優良運転者 |
継続している期間が5年以上、違反やけがのある事故を起こしていない人 |
ゴールド |
|
|
違反運転者 |
違反が複数回ある、けがのある事故を起こしてしまった人 |
青 |
3年 |
免許更新をするときの一連の流れ

運転免許証の更新は、居住地域や所持している免許証の区分などにより、手続きをする場所・講習の内容が異なります。更新手続きが可能な場所や大まかな流れは、更新時期前に届く更新連絡はがきに記載されているため、しっかり確認しましょう。
ここでは、免許を更新するときの一連の流れを詳しく解説します。
更新時期を確認する
免許証の更新を知らせる更新連絡はがきは、更新年の誕生日約1か月前に免許証に記載されている住所宛てに発送されます。更新連絡はがきに記された更新時期と、手続きの内容を確認しましょう。
郵便事故や住所の相違などにより、更新連絡はがきが届かないケースもあります。はがきがなくても更新手続きは可能ですが、受付時間や講習時間は場所により異なるため、事前に警察署や運転免許試験場で確認しましょう。
窓口で受け付けをする
免許更新の期間内に、免許証を更新できる運転免許試験場もしくは警察署へ行き、窓口で受け付けをします。運転免許試験場は、平日の月曜日~金曜日と日曜日に空いている場所が多く、土曜日や祝日は閉館していること大半です。日曜日は混雑しやすいことから、平日よりも待ち時間が長くなるでしょう。
更新はがきが手元にない場合は、受け付けで講習区分の確認が必要です。受付時間が決められている場合もあるため、運転免許試験場や警察署で確認した時間に行きましょう。
適性検査を受ける
更新の受け付けが済んだ後は、運転できる水準かどうかの適性検査を受けます。視覚や聴覚の検査が一般的です。眼鏡をかける方やコンタクトレンズを付ける方は申告し、運転するときと同様の状態で検査を受けましょう。
どちらも運転できる基準に達していない、もしくは各免許の基準に達していない場合は、基準に達した免許の種類での更新となります。さらには、後方の交通確認ができる後写鏡(ワイドミラー)の装着や、聴覚障碍者標識などの標識が必要です。
写真を撮影する
適性検査が終わると、写真撮影に進みます。適切な写真を撮るために、帽子やマスクなど顔が隠れるものは外し、運転時に眼鏡をかける場合は準備しておきましょう。
写真撮影は、運転免許試験場などの係員が行います。顎の引き具合や目線などを指示してくれるため、要望があった場合はしっかりと応えましょう。
中には、持参した写真で申請できる所もあります。自分で写真を用意する場合は、更新案内はがきに記載されている注意事項をよく読み、基準を満たした上で撮影しましょう。
講習を受ける
免許更新の際には、交通ルールを再確認する講習の受講が必要です。免許証の区分によって講習を受ける部屋が分かれており、講習の所要時間も異なります。
どの区分の講習を受ける必要があるかは更新案内はがきに記載されているため、事前に確認しておきましょう。
また、免許更新センターによっては「講習時間が午前と午後に分かれている」「日曜日は優良運転者講習のみ」などの場合もあります。警察署で講習を受ける場合は日時指定もあるため、はがきやWebサイトなどで事前に確認しましょう。
新しい免許証を受け取る
全ての検査、講習が終われば新しい免許証を受け取れます。交付方法は場所によって異なりますが、講習が終わり次第、名前と顔を確認しながら交付されるのが一般的です。
免許更新センターの混雑度合によっては交付までに時間がかかることもあります。更新の日は、なるべく別の予定を入れないようにしましょう。
警察署や一部の免許更新センターでは、即日交付ではなく後日交付の場合もあります。新しい免許証は古い免許証と交換になるため、有効期限間際で更新する場合は、有効期限に注意しましょう。
免許更新の流れ【時間と費用の目安】

運転免許を更新するには、手続きと講習時間を含めるとある程度の時間が必要です。特に混雑が予想される日曜日は、更新に半日かかる場合もあるため、時間に余裕を持って行くことをおすすめします。
また、更新にかかる費用は免許証の区分によって異なるため、更新連絡はがきに記載されている金額を確認しておきましょう。ここでは、免許更新にかかる時間と費用を紹介します。
免許更新の手数料
免許更新に必要な金額は、新しく更新する免許証の区分によって異なります。免許更新の手数料は同一ですが、講習にかかる費用が異なるため、事前に確認しましょう。
|
免許証区分 |
講習手数料 |
更新手数料 |
合計支払額 |
|
優良運転者 |
500円 |
2,500円 |
3,000円 |
|
一般運転者 |
800円 |
3,300円 |
|
|
違反運転者 |
1,350円 |
3,850円 |
|
|
初回運転者 |
|||
|
高齢者講習等受講者 |
0円 |
2,500円 |
これらの手数料は、更新手数料の支払窓口で納付します。警察手数料の支払いは、現金・クレジットカード・電子マネー・QRコード決済が利用可能です。
講習にかかる時間
更新時講習(法定講習)の所要時間は講習区分によって決まっています。具体的な時間は以下の通りです。
|
講習区分 |
講習時間 |
|
優良運転者 |
30分 |
|
一般運転者 |
1時間 |
|
違反運転者 |
2時間 |
|
初回更新者 |
区分によって講習を受ける時間帯が異なり、状況によっては待ち時間が発生するケースもあります。予想以上に時間がかかる可能性があるため、免許更新に出向くときは十分な時間を確保しておくと安心です。
また、講習区分によっては運転免許試験場でしか免許を更新できません。行く予定の場所が、該当の講習区分に対応しているかも併せて確認しましょう。
免許更新の流れ【持ち物】

免許証を更新する際には、さまざまな持ち物が必要です。更新だけであれば、必要な物は運転免許証・はがき・費用のみですが、同時に他の申請も行う場合は証明書や住民票が必要になることもあります。
更新当日に書類の不備がないよう、事前に確認しておきましょう。ここでは、免許を更新するときに必要な書類を紹介します。
必要書類の一覧
運転免許を更新する際に必要な物は「運転免許証」です。更新申請書は各施設で配布しているため、通常の更新であれば運転免許証があれば手続きできます。しかし、状況によっては以下の書類が必要です。
・高齢者講習終了証明書(70歳以上74歳以下の方)
・認知機能検査結果通知書、高齢者講習終了証明書(75歳以上の方)
・写真(持参写真で運転免許を作成する方)
・住民票(更新と同時に記載事項を変更する方)
・在留資格を確認できる書類(外国籍の方)
運転免許に条件が付いている方は、条件に応じて適性試験に使用する眼鏡や補聴器などを持参しましょう。
申請用写真の規定
通常、運転免許を更新するときに申請用写真を提出する必要はありません。しかし、以下の条件に該当する場合は申請用写真が必要なため、事前に準備しておきましょう。
・更新と再交付の手続きを同時に行う場合
・併記の申請をする場合
申請用写真は以下の条件を満たす必要があります。不適切な写真を用意すると撮り直しになるため、提出前に確認するのがおすすめです。
|
申請用写真の基準 |
|
・サイズは縦30mm・横24mm ・無帽(宗教上・医療上の理由がある場合を除く)で撮影 ・正面を向いた上三分身のもの ・無背景 ・申請前6か月以内に撮影 |
持参した写真で免許証を作成したい方は、申請用写真に加えてもう1枚写真が必要です。
免許更新をするときのポイント

運転免許証の更新では、免許更新センターや警察署に行く前に確認しておきたいポイントがあります。必要な書類や更新先の開庁時間などをしっかりチェックしておけば、当日スムーズに免許更新ができるでしょう。
ここでは、免許を更新するときのポイントを3つ紹介します。
満70歳以上になると必要な手続きが増える
運転免許の更新は、満70歳以上になるタイミングで手続きが増えます。運転免許証の有効期間を確認し、末日時点で満70歳以上になる方は高齢者講習の受講が必要です。一般的な更新手続きと流れが異なるため、下記表を参考にしてください。
|
年齢(有効期間満了日時点) |
更新手続きの手順 |
|
70歳以上74歳以下 |
1.有効期間満了日の6か月前以降に高齢者講習を受ける 2.更新期間が始まったら更新手続きを行う |
|
75歳以上 |
1.有効期間満了日の6か月前以降に認知機能検査・高齢者講習を受ける 2.対象者は運転技能検査を受ける 3.更新期間が始まったら更新手続きを行う |
70歳以上になると高齢者講習の受講義務が発生し、終了した人のみが免許を更新できます。75歳以上は認知機能検査も必要です。
認知機能検査の結果によっては、運転免許の取り消し処分を受ける可能性もあります。75歳以上で特定の違反歴がある方は、別途運転技能検査を受ける必要もあり、合格しないと免許は更新できません。
手続きに時間がかかる可能性があるため、70歳以上になる方は6か月前になったら速やかに準備を進めましょう。
施設によって開庁時間が異なる
運転免許を更新できる施設はいくつか設置されていますが、施設によって開庁時間が異なります。
免許を更新するには開庁時間内での手続きが必要です。後日出直すことにならないためにも、事前に開庁時間をチェックしておきましょう。一例として、警視庁が設置している施設の開庁時間は以下の通りです。
|
施設 |
開庁時間 |
|
運転免許試験場 |
平日:8時30分~16時 日曜:8時~11時30分、13時~16時 (土曜・祝休日・年末年始は休み) |
|
運転免許更新センター |
平日:8時30分~16時 (土曜・日曜・祝休日・年末年始は休み) |
|
指定警察署 |
平日:8時30分~11時30分、13時~16時30分 (土曜・日曜・祝休日・年末年始は休み) |
いずれの施設も土曜・休日は閉庁日となっており、日曜日に開庁しているのは運転免許試験場のみです。更新区分によっても利用できる施設や手続きできる時間が異なるため、違反運転者や初回更新者は運転免許試験場での手続きが必要です。
免許更新のはがきは紛失しても受け付けできる
運転免許の更新案内はがきを紛失してしまった場合は、受付窓口で紛失したことを伝えましょう。免許証の区分を確認するのに時間はかかりますが、はがきがなくても更新は可能です。はがきを紛失しても再発行する必要もありません。
しかし、はがきには次の免許証の区分だけではなく更新にかかる費用や更新できる会場、必要な持ち物なども記載されています。内容を覚えていない方や不安な方は、更新センターや試験場のWebサイト、もしくは管轄の警察署に確認しましょう。
2024年から免許更新の予約システムが開始!

免許更新にはさまざまな手続きが必要です。ひとつひとつの手続きに時間がかかることに加え、日曜日に開庁している試験場は特に混雑が予想されます。
そのような背景から、2024年2月1日以降に更新手続きをする場合には、更新手続きの予約が必要となりました。ここでは、更新予約の対象者と予約が不要なケース、予約方法を解説します。
完全予約制の対象者
免許更新の完全予約は、2024年2月以降に手続きする方全てが対象です。更新受け付けの時間を予約するため、受付時間に合わせて向かえば間に合います。受付時間の直前まで予約が可能です。
しかし、完全予約制は全ての都道府県で導入されているわけではありません。「優良運転者のみ予約可」などの地域もあるため、更新案内はがきを確認しましょう。
また、以下の人は予約が不要です。試験場で講習を受ける必要がない高齢者やはがきのない方は、受付時間内に直接手続きに行きましょう。
|
予約が不要なケース |
|
・70歳以上(高齢者講習などの該当者) ・海外旅行や出産が理由で更新期間前の手続きをする方 ・居住地以外の都道府県公安委員会を経由して手続きする方 ・更新連絡はがきがない方 ・島部の警察署で更新する方 |
免許更新の予約方法
運転免許の更新は、各都道府県の警察署が管理するWebサイトから予約できます。警視庁のWeb予約の仕方を一礼として紹介するので、参考にしてください。
1.予約サイトで「運転免許更新の予約はこちら」を選択
2.利用規約を読み同意し、手続きを開始する
3.免許更新(70歳未満)を選択
4.更新連絡はがきに記載された16桁の予約用IDと講習区分を入力
5.予約受付時間を選択して予約完了
予約は1人1件のため、予定を変更する場合はキャンセルし、再度予約が必要です。Webサイトでは24時間いつでも予約できます。
免許更新の有効期間が過ぎた場合の手続きの流れとは?
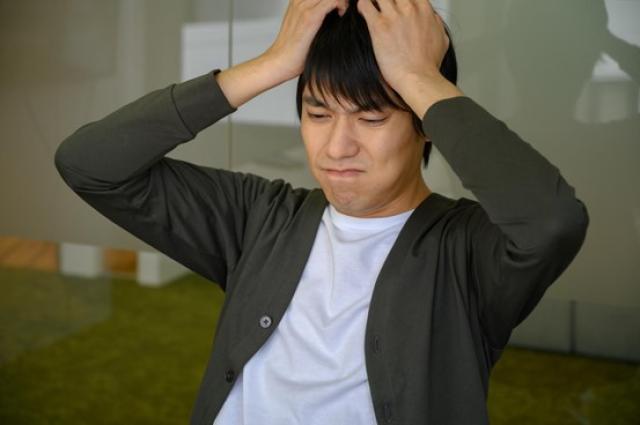
免許更新の期間に間に合わず、有効期間が過ぎてしまった場合には別途手続きが必要です。免許証失効後の期間により手続き内容が異なるため、事前に必要な物、手続きの流れを確認しておきましょう。
ここでは、免許証失効後6か月未満の場合と失効後6か月以降1年未満の場合、失効後6か月以上3年未満の場合の手続きの流れを紹介します。
失効後6か月未満の場合
失効後6か月未満は「うっかり失効」とも呼ばれます。所定の手続きを取れば、本来再取得に必要な学科試験・技能試験の両方が免除可能です。適性試験のみで免許を取得できるため、以下の物を用意して手続きしましょう。
|
・住民票(本籍・国籍などが記載されたもの) ・失効した運転免許証 ・申請用写真 ・高齢者講習終了証明書(70歳以上の方) |
手続きできるのは、運転免許試験場のみです。更新ではなく新規受験扱いとなり、平日しか手続きできない点に注意しましょう。
失効後6か月以上1年未満の場合
失効後6か月を超えていても1年未満の場合は、学科試験・技能試験免除で仮免許を取得できます。試験場に行き適性試験を受ければ仮免許を取得できるため、以下の物を用意しましょう。
|
・住民票(本籍・国籍などが記載されたもの) ・失効した運転免許証 ・申請用写真2枚 |
仮免許を取得した後は、本免許の取得が必要です。普通免許を取得する一般的な手順は以下を参考にしてください。
1.仮免許を取得する
2.指定された時間に路上練習をする
3.試験場で適性試験・学科試験を受け、合格したら技能試験を予約する
4.技能試験を受けて合格する
5.取得時講習を受講する
6.運転免許証を受け取る
失効してから時間が経過すると試験を受ける手間がかかるため、早めの更新を心がけましょう。
失効後6か月以上3年未満経過していてやむを得ない事情がある場合
失効後6か月以上経過していても、失効後3年未満でやむを得ない事情がある場合は、学科試験・技能試験の免除を受けられます。再取得が簡単になるため、下記に当てはまる方は証明書類を用意しておきましょう。
|
やむを得ない状況の一例 |
必要な書類 |
|
入院 |
診断書(疾病名や入退院日が記載されたもの) |
|
海外旅行 |
・パスポート(出入力の証印が押印されたもの) ・法務省による出入国記録など |
|
刑事施設への収容 |
在所証明 |
|
その他公安委員会が認める事情 |
- |
上記の書類以外には、以下の物が必要です。
|
・住民票(本籍・国籍などが記載されたもの) ・失効した運転免許証 ・申請用写真 ・高齢者講習終了証明書(70歳以上の方) |
眼鏡や補聴器などの条件がある場合は、上記と併せて持参する必要があります。
まとめ

運転免許証は、現在所持している免許証の区分によって有効期間が異なります。免許証を確認し、更新案内はがきが届いたら速やかに更新しましょう。更新に必要な持ち物や費用は、はがきに記載されています。
はがきが届かない、紛失した場合は、居住地の警察署に確認しましょう。はがきが手元にない場合でも更新は可能です。免許更新センターや試験場の開庁時間をWebサイトで確認し、所定の時間内に手続きを行いましょう。
▼ライタープロフィール

中村浩紀 なかむらひろき
クルマ記事に特化したライター
現在4台の車を所有(アルファード・プリウス・レクサスUX・コペン)。クルマ系のメディアでさまざまなジャンルの記事を執筆し、2024年1月までに300記事以上の実績をもっている。
豊富なラインアップのネクステージ中古車情報をチェック!
いかがでしたか。今回の記事が中古車購入を検討しているあなたの参考になれば幸いです。
ネクステージでは、他店に負けない数多くの中古車をラインアップしていますので、中古車の購入を検討されている方は、ネクステージの公式Webサイト上で最新の在庫状況をチェックしてみてください。また中古車購入に際して、ネクステージ独自の保証もご準備しております。お気軽にお問い合わせください。


