車検時に納税証明書が見つからない場合はどうする?知っておきたい解決策

車検時に必要な書類のひとつである納税証明書ですが、いざ提出しようとした際に見つからない場合、慌ててしまう方もいるのではないでしょうか。
本記事では、納税証明書の紛失時や発行されていない場合にどのように対処すべきか、具体的な対応方法と解決策について詳しく解説します。
※目次※
4.車検時に納税証明書が見つからない場合|再発行の手続き方法
5.車検時に納税証明書が手元にない場合、受け取っていない可能性がある
・納税証明書は、自動車税が納税済みであることを証明するための書類。
・自動車税の納税証明書が見つからない場合は窓口もしくは郵送で再発行が可能。
・納税証明書は電子的に確認できるケースとできないケースがある。
車検時に提示を求められる納税証明書とは
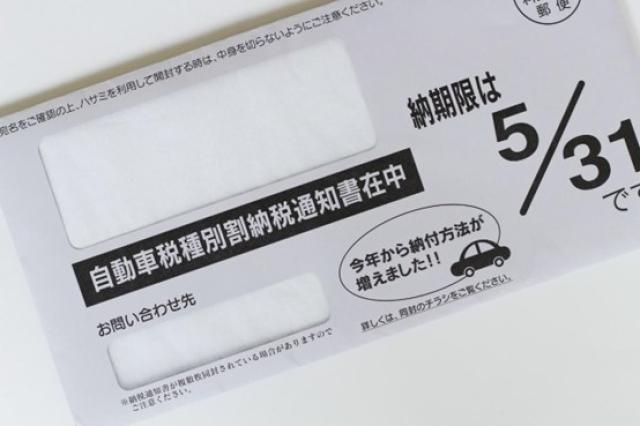
車検時の必要書類として納税証明書が求められますが、その理由が分からない方もいるでしょう。また、特定の条件下では納税証明書の提示が不要となるケースもあります。車検時に納税証明書が見つからない場合は、該当するかどうか確認するのがおすすめです。
ここでは、納税証明書を求められる理由や自動車税納付確認システムについて解説します。
納税証明書を求められる理由
納税証明書は、自動車税が納税済みであることを証明するための書類です。納税証明書には、登録番号や車台番号などの車両情報の他、有効期限や税額などが記載されています。
電子的な自動車税納付確認システムの導入により、納税証明書の提示が省略されるケースも増えていますが、車検時は納税証明書が求められるのが一般的です。
税金を滞納していると車検が受けられないため、納税証明書を提示することで税金の滞納がないことを証明できる役割を持っています。
納税証明書は電子的に確認できる?
2015年4月以降、自動車税納付確認システムJNKS(ジェンクス)、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が運用されています。このシステムは、軽自動車検査協会・運輸支局などが自動車税の納付状況を電子的に確認するためのものです。
これにより、車検時に納税証明書が手元にない場合に提示を省略できるケースが増えました。ただし、電子的に納税を確認できないケースもあるため、納税証明書を受け取った場合は大切に保管するようにしましょう。
納税証明書が電子的に確認できないケース
電子的に自動車税納付確認ができないケースは主に「自動車税を納付していない」「自動車税納付後すぐに車検を受ける」場合です。納付直後はシステムに反映されていない可能性があるため、納税証明書が必要になることがあります。
自治体によって電子的に確認ができるようになるまでの期間が異なるため、納税証明書なしで車検を受けたい場合は、早めに自動車税を納めておきましょう。また、システムに反映されるまでの期間は最大で4週間程度が目安です。
車検時に必要な納税証明書はどこでもらえる?
税納税証明書は、毎年5月ごろに順次発送される納税通知書の右端にあります。この納税通知書を使用して金融機関の窓口やコンビニで納付すると、領収印を押して受け取れる仕組みです。
一方で、他の納付方法を選択すると納税証明書が発行されないケースがあります。すぐに車検を控えている場合は、窓口で納付して納税証明書を受け取るのがおすすめです。
車検時に納税証明書が見つからない場合|再発行の手続き先

電子的に納税を確認できず、納税証明書の提示を省略できないこともあるでしょう。紛失した場合には再発行の手続きが必要ですが、普通自動車と軽自動車では納税証明書の再発行を行う手続き先が異なるため注意が必要です。
ここでは、普通自動車と軽自動車のそれぞれの手続き先を紹介します。
普通自動車の自動車税納税証明書が見つからない場合
普通自動車の自動車税は、都道府県税です。納税証明書が見つからない場合は、自動車税事務所や都道府県税事務所もしくは管轄の運輸支局で再発行の手続きを行いましょう。
納税後に他の都道府県に転居した場合、納税地で再発行の手続きが必要です。
軽自動車の納税証明書が見つからない場合
軽自動車の自動車税は、市町村税です。納税証明書が見つからない場合は、市役所や区役所などの窓口で再発行の手続きを行いましょう。
納税後に他の市区町村に転居した場合、納税地で再発行の手続きが必要です。
車検時に納税証明書が見つからない場合|再発行の手続き方法

車検時に納税証明書が見つからない場合は、普通自動車と軽自動車のそれぞれの手続き先で再発行を行いましょう。取得するには、窓口で手続きする方法と郵送で手続きする方法があります。
ここでは、それぞれの再発行手続きの方法を確認しましょう。
窓口での再発行手続き
窓口での再発行手続きを行う場合は、事前に必要書類をそろえた上で普通自動車・軽自動車それぞれの手続き先に行きましょう。多くの場合、詳細はWebサイトで調べられます。なお、納税証明書の発行手数料は、ほとんどの自治体でかかりません。
主に求められるのは、自動車の登録番号、車台番号を確認するための「車検証」や「本人確認書類」が代表的です。代理人が申請する場合は、委任状を求められることもあるでしょう。
窓口で納税証明書交付請求書を受け取り、必要事項を記入します。なお、納税証明書自動発行機がある場合は不要です。
郵送での再発行手続き
郵送で再発行手続きを行う場合は、事前に送付先の窓口へ問い合わせましょう。必要な物は基本的に窓口での手続きと同じですが、窓口で確認できないため車検証の写しや本人確認書類の写しを求められることもあります。
上記に加えて、納税証明書交付請求書や返信用封筒(切手貼付)を自分で用意する必要があります。指定の住所に送付したら、納税証明書が届くまで待ちましょう。
車検時に納税証明書が手元にない場合、受け取っていない可能性がある

車検時に納税証明書が手元にない場合、受け取っていない可能性があります。自動車税の支払いは自治体によって異なりますが、キャッシュレス決済で納付すると納税証明書が発行されない自治体も多いため、支払い方法を思い返しましょう。
ここでは、代表的なキャッシュレス決済について解説します。
クレジットカード
クレジットカードで自動車税を納付した場合、税納税証明書を発行しない自治体もあります。自治体によっては自宅に郵送することもあるため、事前に確認しましょう。
また、クレジットカードで自動車税を納めた後、納税証明書が手元に届くまでに時間がかかる場合があります。納税手続きを完了してから納税証明書を取得するまでに時間を要する場合があるため、事前に余裕を持って手続きを進めることが重要です。
スマートフォン決済
スマートフォン決済で自動車税を納付した場合も同様に、税納税証明書を発行しない自治体もあります。自治体によっては自宅に郵送することもあるため、事前に確認しましょう。
また、スマートフォン決済で自動車税を納めた後、納税証明書が手元に届くまでに時間がかかる場合があります。納税手続きを完了してから納税証明書を取得するまでに時間を要する場合があるため、事前に余裕を持って手続きを進めることが重要です。
Pay-easy(ペイジー)
2023年4月以降、地方税共同機構(LTA)が運営する「地方税お支払サイト」において、日本全国ほぼ全ての都道府県や市区町村の自動車税・軽自動車税がPay-easy(ペイジー)で支払えるようになりました。
ぺイジーは、パソコンやスマートフォンを利用したネットバンキングや、ATMから自動車税を納付する方法です。ただし、コンビニ窓口・コンビニの共用ATMでは使えないため注意しましょう。
ペイジーで自動車税を納付した場合も、納税証明書を発行しない自治体が多い傾向です。自治体によっては自宅に郵送することもあるため、事前に確認しましょう。
まとめ

税金を滞納していると車検が受けられないため、自動車税が納税済みであることを確認するために納税証明書の提示が求められます。
納税証明書が見つからない場合、電子確認によって提示を省略できるケースがありますが、再発行が求められるケースも少なくありません。車検を直近に控えている場合は、金融機関やコンビニで支払い納税証明書を受け取るのがおすすめです。
自動車税は車が古くなると増税されます。ディーゼル車は11年、ガソリン車は13年経過で負担が大きくなるため、このタイミングで車を買い替えるのもおすすめです。
▼ライタープロフィール
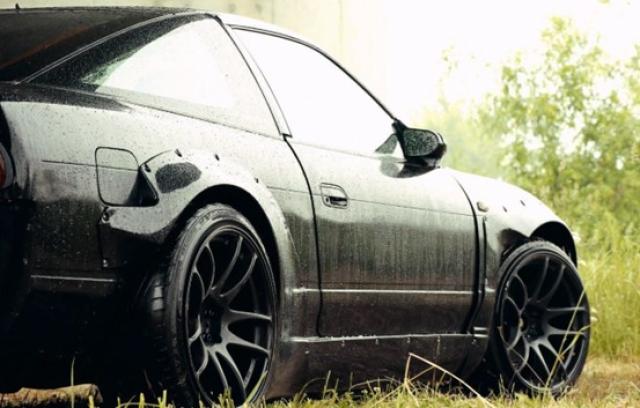
松田 莉乃
過去の愛車は32GT-R、180SX、33Z。車の構造に興味を持ち「自分の車は自分で作りたい」という気持ちから自動車整備工場に勤務した経験を持つ。中古車買取査定員やタウン情報誌の編集部として仕事をした経験を活かし、主に車・タイヤ関係のメディアを対象に2020年からフリーランスのライター兼エディターとして活動中。
豊富なラインアップのネクステージ中古車情報をチェック!
いかがでしたか。今回の記事が中古車購入を検討しているあなたの参考になれば幸いです。
ネクステージでは、他店に負けない数多くの中古車をラインアップしていますので、中古車の購入を検討されている方は、ネクステージの公式Webサイト上で最新の在庫状況をチェックしてみてください。また中古車購入に際して、ネクステージ独自の保証もご準備しております。お気軽にお問い合わせください。


